紫式部は恋愛上手だったのか? 光源氏に似た「インテリ貴公子」との関係とは
日本史あやしい話41
■道長の思惑
具平親王とは、前述のごとく、村上天皇の第七皇子という極め付けの貴種である。生まれは964年というから、紫式部よりも10歳前後年上のはず。詩歌や書にも優れ、当時の文壇の中心人物と目された御仁であった。
ここで少々、系譜をたどってみよう。紫式部にとって具平親王は、祖父・雅正の義理の姉妹の孫にあたる。叔父・為頼と具平親王の母・荘子は従兄妹同士で、さらに、紫式部の従兄の伊祐の養子・頼成は、実は具平親王の子(平貞盛の娘と通じて生ませたとも。そればかりか、親王と紫式部の間に生まれた子だったとの説まである)だったとか。このような姻戚関係に加え、為時が具平親王家の家司として仕えていた可能性まで指摘されている。
それらが事実かどうかはともあれ、具平親王と為時は親しく、頻繁に親王家(六条殿、別名・千種殿)に出入りしていたことは間違いなさそうだ。一説によれば、その親しい間柄ゆえに、紫式部自身が親王家に童子として仕えていたと見られることもある。漢籍好きな紫式部のことゆえ、親王家の蔵書に惹かれて、あしげく通っていたとも考えられるのだ。
この為時家と親王家との親密な付き合いを道長が知って、紫式部に近付いたとも考えられるかもしれない。権勢を極めた道長にとって、最後の願いともいうべきが、皇族の尊貴な血を自らの子孫に受け継がせようというものであった。
そのため、息子・頼通を具平親王の娘・隆姫と結婚させたいと願っていた。その橋渡し役として、紫式部に白羽の矢が立ったのではないか。
その思惑を含んだ歌が、『紫式部日記』に記された「中務の宮わたりの御事を御心に入れて、そなたの心よせ有る人とおぼして、語らせたまふ」という一文だと考えられるのだ。
「中務の宮」とは、具平親王のこと。「宮わたりの御事を御心に入れて」とは、道長が息子・頼通を親王の娘・隆姫と結婚させたいと願っていたことを表している。
問題は、その後に記された「心よせ有る人」である。これは、単に縁故ある人ととらえることもできそうだが、「好意を寄せる人」と捉える方がふさわしい。好意を寄せるのが紫式部側か具平親王側かはわかりにくいが、ともあれ、二人が思いを寄せていることを道長が感じ取っていたのだろう。
「語らせたまふ」とは相談を持ちかけることだから、その具平親王と親しい紫式部に対して、息子の結婚について相談を持ちかけたというのだ。
となると、道長にとって紫式部は、『源氏物語』を書かせて彰子の元に一条天皇をおびき寄せるために必要な人材であったというだけでなく、具平親王家との血縁を結ぶための橋渡しとしても重宝していたということになる。紫式部が彰子の元へと送られた(1006年前後)のも、この役割を担わせるためだったと考えることもできるのだ。
ちなみに、その後、頼通と隆姫は道長の思惑通り結婚することができたが、残念ながら二人の間に、子は生まれなかった。そこで行われたのが、具平親王の子・師房(雑仕女に生ませた子だったとの説も)を頼通の養子として迎えるというものであった。
これが、後の村上源氏へと系譜をつないでいくことになる。具平親王が藤原氏による摂関政治に批判的だったと見られることもあるが、その子孫が源氏勢力を盛り返したというのは、なにやら因縁めいて興味深い。
画像出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)
- 1
- 2

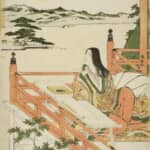


-e1704957789649-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
